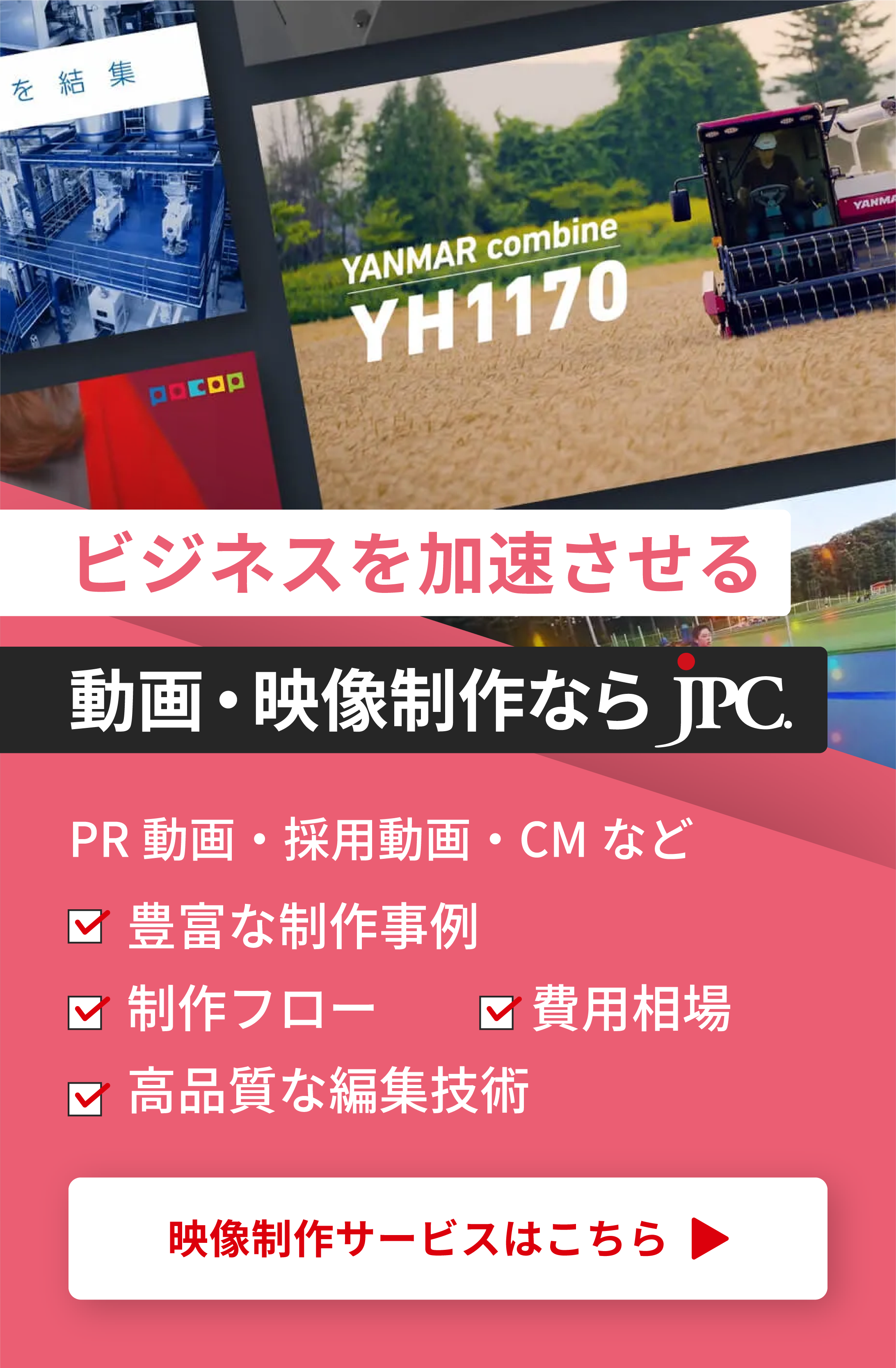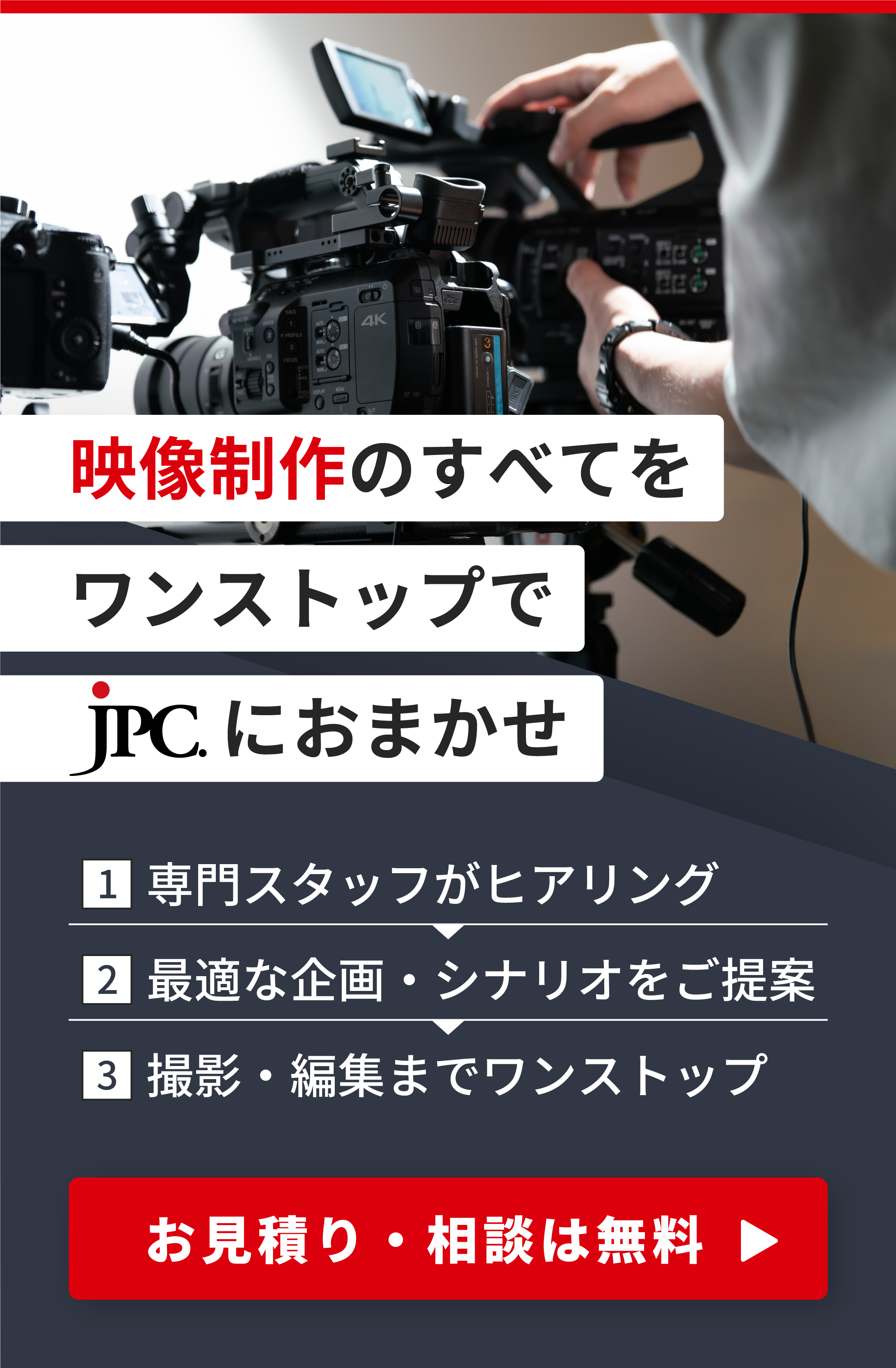2025.09.05
動画制作にかかる期間はどのくらい?依頼から納品までの流れを解説!

会社紹介動画やサービス紹介動画・採用動画・IR動画など、企業が動画コンテンツを活用するケースは増えています。その一方で、「動画制作にはどのくらいの期間がかかるのか?」と気になる方も多いのではないでしょうか。
動画制作に必要な日数は、内容や工程によって異なりますが、全体スケジュールの目安を把握することは、企画段階でも非常に重要です。
この記事では、動画制作の流れと必要な期間の目安について、映像制作会社の視点からわかりやすく解説します。
納品までのスケジュール感を知りたい方は、ぜひご覧ください。
動画制作の工程
まずは基本的な情報として、動画制作に必要な工程をご紹介します。全体のスケジュールを把握するうえでも、各ステップで何を行い、どれくらいの期間がかかるのかを知っておくことが大切です。

- 企画・構成
- 絵コンテ・撮影準備
- 撮影・素材集め
- 編集・MA・ナレーション収録
- 最終調整・納品
各工程の内容と必要日数の目安を見ていきましょう。
関連記事:動画制作の流れ(フロー)とは?各工程の手順やポイントを解説
1.企画・構成(目安:5~10日)
「企画・構成」は、映像制作会社のクリエイターやディレクターが、発注企業の目的や希望をヒアリングし、動画の構成やシナリオ(台本)を作成する工程です。この初回の打ち合わせは、「キックオフ」と呼ばれることもあります。
企画・構成工程にかかる日数は、動画の尺(映像時間)に影響されることもあれば、企画内容を審査するクライアント企業に影響されることもあります。
スムーズに進めば5日〜7日程度で次の工程へ進めますが、10日以上かかることも珍しくはありません。
2.絵コンテ・撮影準備(目安:7~14日)
一通りの動画構成が決まったら、それを「絵コンテ」として具体化します。絵コンテとは、各シーンのビジュアルイメージをイラストやカットで表現した資料で、発注者と制作会社が映像の完成イメージを共有するために不可欠な工程です。
絵コンテが初稿で完成することは珍しく、ブラッシュアップを重ねていくケースがほとんど。短ければ数日、修正を重ねる場合は7日以上は見込んでおきましょう。
絵コンテが完成し、撮影が必要なシーンが確定したら、撮影準備にとりかかります。ロケハン(撮影現場の下見)や撮影機材の確保、演者やナレーターのオーディション(キャスティング)、撮影スケジュール調整などさまざまな準備が必要なため、10日程度は見込んでおきましょう。
3.撮影・素材集め(目安:1~3日)
「撮影」は基本的に1日で完結させることが多いです。ただし、撮影場所が複数ある場合や、撮影対象のスケジュールがつけられない場合には、2〜3日に分けて撮影することもあります。
また、撮影と並行して、映像に使用する素材データの収集も行います。たとえば企業ロゴ、スライド資料、製品画像、グラフィック素材などが該当します。
これらの素材集めは撮影準備〜撮影の間に完了することが多く、制作全体のスケジュールに大きな影響を与える工程ではありません。
4.編集・MA・ナレーション収録(目安:7~21日)
素材が集まったら「編集」工程に進みます。一般的な実写中心の動画であれば、編集作業にはおおむね2〜3週間(10〜21日程度)を見込むのが一般的。ただし、3DCGやVFXなどの高度な表現を含む動画の場合は、作業量が多くなるため、編集期間が1ヶ月以上に延びるケースもあります。
3DCG・VFX
3DCG(3次元コンピュータグラフィックス):実写で撮影できない構造物やシーンを仮想空間で再現する技術。
VFX(Visual Effects):実写映像に合成や加工を施して演出する技術。幻想的な空間や非日常的な世界観の演出などに使われる。
映像が完成したら、次はMA(音声調整)とナレーション収録に進みます。
MA(Multi Audio)
音楽・効果音・ナレーションなどの音声を追加・調整して、最終的な音響設計を仕上げる工程。
ナレーション収録は、スタジオで行う場合と、ナレーターの自宅で録音する「宅録」を活用する場合があり、宅録で対応できる内容であれば、数日程度で完了することも十分可能です。
5.最終調整・納品(目安:2~5日)
映像と音声の編集が完了したら、クライアントによる最終チェック(試写)が行われます。
この段階では、テロップの誤字や音量バランスなど、軽微な修正対応が主な内容になります。
修正が少ない場合は2〜3日程度で対応可能ですが、確認フローが多段階だったり、追加要望がある場合は5日前後かかるケースも。
最終データは、納品形式(ファイルの種類や解像度など)を確認のうえ、オンラインストレージやメディアを通じて納品されます。
【種類別】動画制作にかかる日数の目安
動画制作と一口に言っても、その内容によって必要な工程やスケジュールは大きく変わります。
たとえば、撮影が必要な実写映像と、イラストや文字、グラフィック素材のみで構成される動画では、制作日数の目安も異なります。
それぞれ制作にかかる日数がどのくらい違うのか比較してみましょう。
グラフィック素材のみの動画(目安:約3~4週間)

実写撮影を伴わない、イラストアニメーションやモーショングラフィックスだけで構成された映像は、制作工程が比較的シンプルなため、1ヶ月以内での納品も可能です。
モーショングラフィックス
静止した文字・ロゴ・イラスト・図解などに動きを加え、映像として表現する技術。
こうした動画では、ヒアリングと企画構成に約2週間、編集・調整作業に約2週間を目安に進行できます。とくに5分以内の尺であれば、制作開始から3〜4週間での納品も可能になるでしょう。
撮影素材も含めた動画(目安:約6~8週間)

撮影を伴う映像制作では、グラフィック素材のみで構成された動画と比べて工程が多く、全体の制作期間も長くなりがちです。
たとえば、以下のような準備作業が必要になります。
- ロケハン(撮影場所の下見)
- 機材・出演者の手配(キャスティング)
- 香盤表の作成や撮影スケジュールの調整
こうした工程には、最低でも1〜2週間は確保しておきたいところ。
また、撮影が1日で終わらない場合や、天候・関係者の都合による日程変更が発生するおそれもあるため、スケジュールには余裕を持たせておくべきでしょう。
さらに、実写映像や収録素材のバリエーションが増えることで、編集作業の負担も増していきます。
編集〜MA(音声調整)〜ナレーション収録などの仕上げ工程には、おおよそ3週間前後を見込んでおくのが現実的です。
短納期で動画を制作するための7つのポイント
動画制作には通常1〜2ヶ月程度の期間が必要ですが、プロモーション施策や社内イベントの都合により、できるだけ短期間で納品したいという要望も少なくありません。
こうした短納期の案件では、納品日から逆算してスケジュールを組み立て、限られた工程をいかに効率化できるかが鍵となります。
こちらでは、スケジュールに余裕がないときでも動画のクオリティを維持するために有効な7つの工夫をご紹介します。

- 動画のイメージをあらかじめ明確にしておく
- 動画に使える素材は積極的に提供する
- 動画の尺を短縮する
- グラフィック素材のみの動画にする
- フリー素材を活用する
- 納期から作る動画の内容を考える
- ナレーションが必要な場合は「宅録」を活用する
それぞれのポイントについて詳しく解説します。
1.動画のイメージをあらかじめ明確にしておく
動画の完成イメージを事前に言語化・視覚化しておくことで、「企画・構成」や「絵コンテ」の作成にかかる時間を大幅に短縮できます。
以下のような準備をしておくと、制作会社とのやり取りもスムーズになります。
- 参考動画をいくつかピックアップしておく
- 伝えたいメッセージを明確にする
- 想定しているターゲット(視聴者層)を具体化する
- 使用する媒体(YouTube・Web・SNSなど)を決めておく
こうした事前情報が揃っていれば、キックオフから1週間以内に撮影準備へ進めることも十分可能です。映像制作会社との認識のズレも最小限に抑えられるため、ヒアリングや企画書作成にかかる時間も短縮しやすくなるでしょう。
2.動画に使える素材は積極的に提供する
制作期間を短縮するうえで非常に効果的なのが、使用できる素材をあらかじめまとめて提供しておくこと。過去に撮影した映像や写真、ロゴデータ、プレゼン資料、字幕原稿など、動画制作に使える素材は依頼主側から積極的に共有しておくと、やり取りの回数を減らせます。
とくに絵コンテ作成の前までに必要な素材が揃っていれば、撮影や編集の工程を効率よく進められるでしょう。
▼活用しやすい素材の例
- ロゴデータ(AI・PNG形式など)
- 過去の社内動画や記録映像
- 商品・サービスの写真
- スライド資料や提案書
- 字幕テキスト(ナレーション台本)
また、制作会社が混乱しないように、素材ごとにフォルダ名を工夫するのもひとつのポイント。たとえば、「ロゴデータ一式」「○○事業部 撮影素材」などのように明記しておくと、確認や分類の手間を省けます。
「あとで追加する」より、「最初に渡せるものはすべてまとめて提出する」という姿勢が、結果としてスケジュール短縮につながるはずです。
3.動画の尺を短縮する
動画の「尺(再生時間)」が長くなるほど、編集作業の工数や確認作業が増え、結果として制作期間も延びやすくなります。そのため、納期を重視する場合は、動画の尺をできるだけ短く設計することが現実的な対応策といえるでしょう。
とくに、社内報告・商品紹介・採用動画など、情報を簡潔に伝えることが目的のコンテンツでは、要点をコンパクトにまとめることで視聴効果も高まり、完成までの時間も短縮しやすくなります。
目安として、1〜2分以内に収まる構成であれば、通常よりも短い制作スケジュールで納品できる可能性が高まります。
ここで重要なのは、「情報を削る」のではなく、伝えるポイントを明確に絞り込むこと。視聴者にとって伝わりやすく、かつ制作効率も上がる構成を目指しましょう。
4.グラフィック素材のみの動画にする
実写撮影を伴う動画制作では、「スケジュール調整」や「撮影準備」に1〜2週間程度を要することが一般的。さらに、撮影素材が多くなるほど、編集工程の工数も増加しがちです。
そのため、納期を優先したい場合は、あえてグラフィック素材のみで構成された動画を選択するのもひとつの方法です。
構成や演出の幅は制限されますが、スケジュール短縮には非常に効果的な選択肢といえるでしょう。
たとえ実写を使わない構成であっても、ナレーションやBGMを効果的に組み合わせることで、十分な訴求力を持った動画に仕上げることは可能です。
5.フリー素材を活用する
たとえグラフィック中心の動画(アニメーション動画やスライドショー形式など)であっても、すべての素材をオリジナルで制作する場合は、実写映像と同等の制作日数がかかってしまうことも。そのため、制作期間を短縮したい場合は、商用利用が可能な「フリー素材」を積極的に活用することが有効です。
近年は、グラフィック素材に限らず、映像・BGM・ナレーション音声などの商用利用可能な素材も数多く存在します。映像制作会社が汎用的なフリー素材をストックしているケースもあるため、あらかじめ「フリー素材の活用を検討している」と伝えてみてください。
6.納期から作る動画の内容を考える
展示会やイベントなど、「いつまでに動画を完成させる必要があるか」が明確な場合は、期日から逆算して映像コンテンツの内容を設計するのがおすすめです。
たとえば、納期までに3ヶ月程度の余裕があるケースであれば、モーショングラフィックスや実写撮影素材、3DCGなどを組み合わせたリッチな映像表現も十分に実現できます。
一方で、納期が2週間を切っているようなタイトなスケジュールの場合は、企画や構成は既存のものやテンプレートを活用し、グラフィック中心のシンプルな構成に絞り込むほうが現実的でしょう。
制作期間に応じてどのような映像コンテンツが最適なのか、映像制作会社に相談してみてください。
7.ナレーションが必要な場合は「宅録」を活用する

ナレーションの収録方法には、「スタジオ収録」と「宅録(ファストレコーディング)」の2種類があります。スケジュールを短縮したい場合は、宅録を活用するのがおすすめです。
スタジオ収録では、ナレーターにその場で指示を出しながら録音できるため、テレビCMや高音質が求められる映像制作に適しています。ただし、スタジオの空き状況やナレーターのスケジュールを調整する必要があるため、収録までにある程度の期間を見込む必要があります。
一方、「宅録」はナレーターが自宅の録音機材を使って音声を収録する方法で、最短1営業日〜1週間程度で納品が可能です。近年はナレーターが保有する機材の性能も向上しており、企業VP(ビデオパッケージ)やWeb動画のナレーション用途であれば、宅録でもまったく問題ありません。
とくに短納期の案件では、宅録対応のナレーターを手配してくれる制作会社に依頼することで、スケジュールの見通しも立てやすくなります。
なお、JPCでも宅録対応のナレーター手配・ディレクションを含めた一貫対応が可能ですので、お気軽にご相談ください。
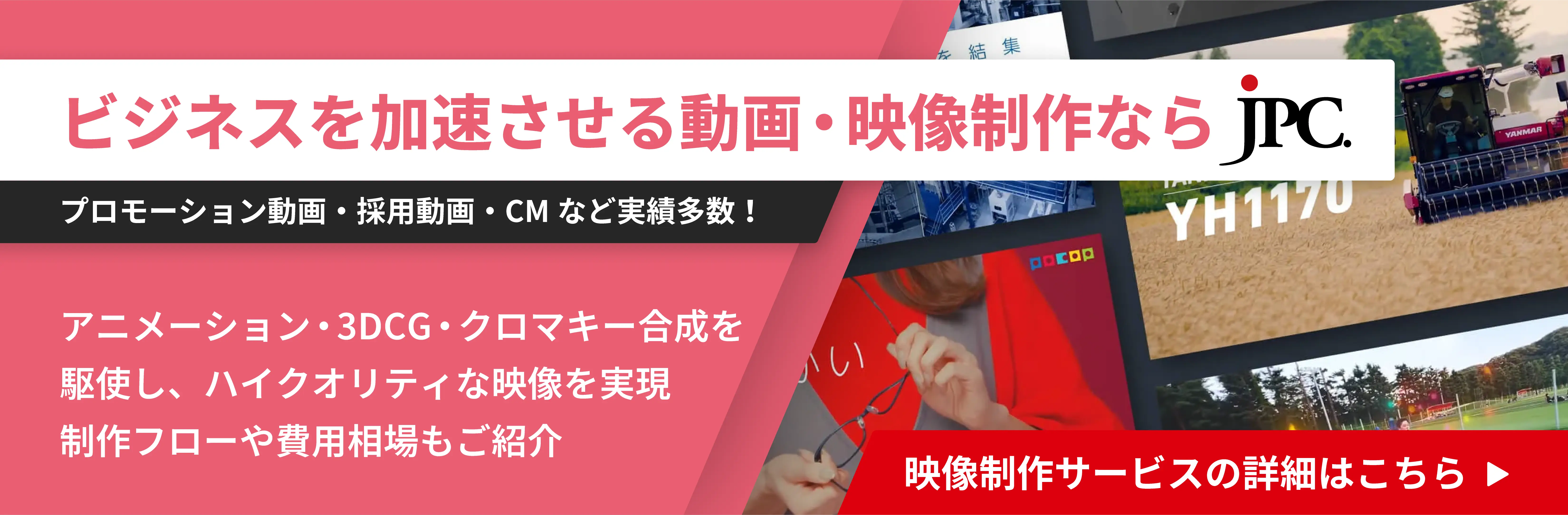
短納期で動画を制作するときに注意すべきこと
短納期での動画制作は、通常よりも工程の密度が高く、判断の速さと段取りの正確さが求められるハイレベルな案件です。とくに、構成やシナリオに十分な時間をかけられなかったり、撮影や編集の工程に余裕がない場合には、仕上がりに粗さが残るリスクも否めません。
ただし、次の5つのポイントに注意しておけば、限られた期間内でもクオリティの高い動画を完成させることは十分可能です。

- 実績が豊富な映像制作会社に依頼する
- 複雑な表現技法は用いない
- 現実的なスケジュールを組む
- 動画制作に必要な資料・素材はあらかじめ用意しておく
- 通常より予算を多く用意しておく
それぞれの注意点についてくわしく解説しますので、動画制作に失敗したくない方はぜひ参考にしてみてください。
実績が豊富な映像制作会社に依頼する
短納期でありながら高品質な動画を完成させるには、それ相応の実力が必要です。実績が乏しい映像制作会社や、短納期案件に慣れていないチームに依頼してしまうと、スケジュールの遅延やクオリティの低下といったリスクが高まります。
一方で、短納期にも柔軟に対応してきた実績のある映像制作会社であれば、限られた時間の中でも工程を整理し、想定外のトラブルにも的確に対応できます。
「動画の品質を維持しつつ、納期も守る」という観点から考えると、実績豊富なプロに依頼することが、最も重要なスタート地点といえるでしょう。
複雑な表現技法は用いない
短納期で動画を制作する際には、「表現の難易度」と「必要日数」のバランスを見極めることが非常に重要です。
たとえ高いスキルを持つ制作会社であっても、3DCGやVFXなどの複雑な表現技法を短期間で仕上げるのは至難の業。こうした技法は高い表現力を持つ一方で、制作工程が増え、確認や修正の回数も多くなるため、スケジュールに余裕のない案件には不向きです。
短納期でも安定したクオリティを確保したい場合は、モーショングラフィックスや実写+ナレーションによるシンプルな構成に絞るのが現実的です。制作スケジュール全体を柔軟にコントロールしやすくなるという点でも、有効な判断といえるでしょう。
現実的なスケジュールを組む
どれだけ工程を効率化したとしても、一定のクオリティを維持した動画を制作するには、最低でも2週間程度の期間が必要です。それより短い納期を設定してしまうと、どこかの工程で品質・段取り・確認のいずれかが破綻する可能性が高くなります。
短納期プロジェクトでありがちなのが、「スケジュールありき」で進行してしまい、結果として内容が薄くなる・確認不足でミスが残る・意図が伝わらない映像になるといったリスクが発生するケース。
だからこそ、納品までに確保できる実働日数を冷静に見極めたうえで、制作会社と現実的なスケジュールを相談しておくことが欠かせません。
「とにかく早く作る」ことだけに注力するのではなく、「納品後にしっかり活用できる完成度」を最優先すべきでしょう。その視点こそが、動画の効果を最大化させる土台になるはずです。
動画制作に必要な資料・素材はあらかじめ用意しておく
すでに触れたように、制作スケジュールを短縮したい場合は、必要な資料や素材を事前に揃えておくことが不可欠です。短納期のプロジェクトでは、「あとから素材を渡す」では間に合わない場面も多く、準備の早さがそのまま納品スピードに直結するといえるでしょう。
制作会社から「この資料をください」と言われてから対応するのではなく、必要になりそうな情報を先回りして整理・共有しておくことが理想的です。
通常より予算を多く用意しておく
短納期で動画を制作する場合、「スピード」を確保するために、通常よりも多めの予算を見込んでおくことが大切です。限られた時間の中で工程を圧縮するには、追加の人員確保や稼働調整に伴うコストの発生は避けられません。
たとえば、ナレーションを宅録や即納対応で依頼する場合、通常よりも高めの費用がかかるケースもあります。また、撮影準備を短期間で進めるために関係者を追加したり、編集スタッフの夜間対応が発生したりすることで、制作費用全体が上振れする可能性もあるでしょう。
こうした背景から、短納期案件では「特急料金」や「短納期対応費」などの加算項目が発生することも珍しくありません。納期と制作費用はトレードオフの関係にあることを、あらかじめ理解しておきたいところです。
まとめ
企業紹介・サービスPR・採用・IRなど、さまざまなビジネス用途で活用される動画制作では、キックオフから納品までにかかる期間は、一般的に約50〜60日(約2ヶ月)が目安とされています。工程が順調に進んだ場合でも、最低でも約28日(4週間)は必要と考えておきたいところです。
一方で、グラフィック中心の短尺動画であれば、工夫次第で2週間前後の納品も現実的でしょう。ただしそのためには、素材の事前提供や尺の調整、構成の簡略化など、この記事でご紹介したポイントを的確に押さえる必要があります。
JPCでは、企画・撮影・編集・MAまでを社内で一貫対応しており、短納期案件にも柔軟に対応できる制作体制を整えています。
「展示会に間に合わせたい」「限られた予算で最適なプランを相談したい」といったご要望にも対応可能です。
企業動画の納期やスケジュールでお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。