2025.03.31
ランディングページ作成の流れを解説!LP制作のポイントや注意点とは?

ランディングページ(LP)は、画像やアイコンなどのデザインを通じて企業の商品やサービスを視覚的にアピールし、販売促進やブランド認知を高める強力なツールです。また、解析ツールによる分析と改善がしやすい点も、ランディングページを制作する大きなメリットといえるでしょう。
しかし、「どのような流れでランディングページを制作するのかがわからない」という方も多いのではないでしょうか。
本記事では、制作の流れやポイント、LP制作を成功させるコツまで、Web制作会社の視点から詳しく解説します。LPの制作事例もご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
ランディングページ(LP)制作の流れ|全体像
制作の流れ|全体像-1024x538.jpg)
ランディングページの制作は、以下の流れで行います。
- 目的・ターゲットの明確化
- 企画構成(ワイヤーフレーム作成)
- デザイン作成
- コピーライティング
- コーディング
- 公開
- 効果測定・改善
各工程で行う内容やポイントを解説します。
1.目的・ターゲットの明確化
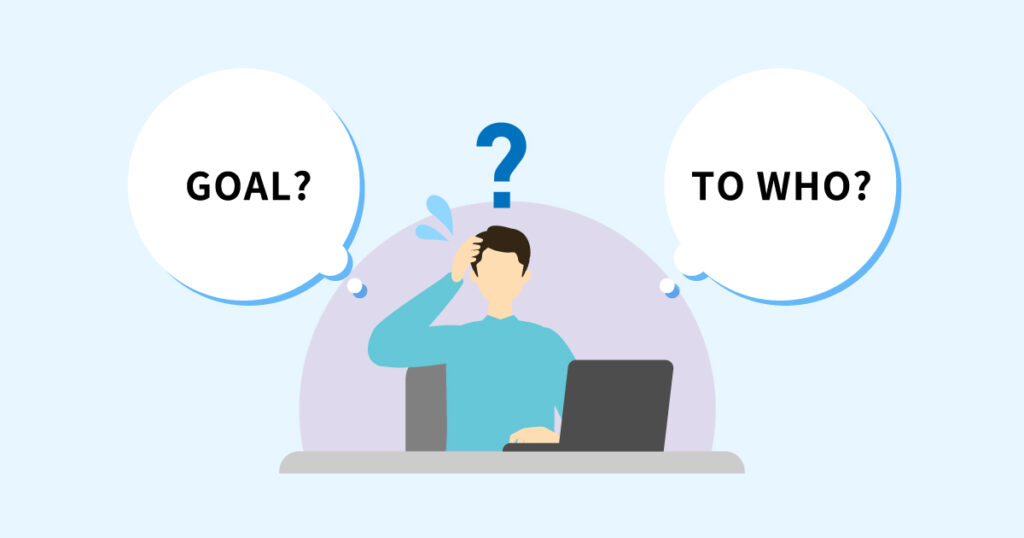
ランディングページ制作においては、新規・リニューアルいずれの場合も、まず「何を達成したいのか」「誰に向けて制作するのか」を明確にすることが重要です。
たとえば、商品やサービスのPRが目的であれば、購買に結びつく年齢、性別、興味関心などを意識し、販売促進につながるターゲット層を具体的に設定します。BtoB向けサービスの場合は、リード獲得を目的に業種や企業規模、意思決定者の役職などを細かく定めておくとよいでしょう。
ブランドイメージの向上や認知度の拡大が目的の場合も、ターゲット顧客層を設定し、どのような表現でブランドイメージを伝えるかを考えることが大切です。
最初に目的とターゲットを明確にしておくと、LPの各要素を目的達成に向けて最適化することが可能なため、より効果的なLPを制作できるようになります。
2.企画構成(ワイヤーフレーム作成)
目的とターゲットが決まったら、ランディングページ全体の設計図である「ワイヤーフレーム」を作成します。
ワイヤーフレームとは、ランディングページ内のヘッダーやメインビジュアル、CTAなど、各要素の配置を示したもののこと。これにより、ユーザーの目線の動きや情報の優先順位を考慮し、目的達成に向けて最も効果的なレイアウトを検討できます。
3.デザイン作成
ワイヤーフレームをもとに、ランディングページのデザインを作成します。デザインを作成するうえでは、機能性と美しさの両立が重要なポイントに。ターゲット層にあわせた色使いやフォント、画像を選定し、ブランドイメージと一貫性のあるデザインを意識しましょう。
たとえば、若者向けの商品であれば鮮やかな色使いや動きのあるデザイン、高級商品なら落ち着いたトーンと余白を生かしたデザインを採用するなど、ターゲットにあわせた工夫が必要です。
4.コピーライティング
デザインが完成したら、次にコピーライティングを行い、ターゲットの行動を促す魅力的な文章を作成します。
キャッチコピーでは、数文字のフレーズで商品やサービスの特徴を簡潔かつ印象的に表現し、ユーザーの興味を引きつけることが重要に。本文では、ターゲットの課題や悩みに寄り添いながら、商品やサービスの詳細を丁寧に説明します。
また、ランディングページのライティングにおいては、SEO対策も意識し、重要なキーワードを自然に盛り込むことがポイントです。
5.コーディング
デザインとコピーが確定したら、ランディングページをWebページとして実装します。HTMLやCSS、JavaScriptを使用して、デザインカンプどおりの見た目と機能を再現しましょう。
また、コーディングでは表示速度の最適化も重要なポイントに。画像の圧縮やコードの軽量化を行い、ページの読み込み時間を短縮します。
コーディングが完了したらテスト環境にアップロードし、各ブラウザでの表示確認や機能の動作確認を行います。フォームの送信テストやリンクの確認など細部にわたる検証を行い、不具合が見つかった場合は修正しましょう。
6.公開
テスト環境での確認が完了したら、ランディングページを本番環境で公開します。公開後は、実際のユーザー環境で表示や動作に問題がないか最終確認を行いましょう。また、SEO対策として、サイトマップの送信やrobotsファイルの設定を行い、検索エンジンで上位表示されやすくすることも重要です。
Web制作会社に依頼した場合は、CMSの操作方法や更新手順の説明が行われたり、公開後の更新や不具合対応といったサポートが提供されたりするケースが一般的です。
7.効果測定・改善
ランディングページの公開後は、継続的な効果測定と改善が重要になります。アクセス解析ツールを活用してユーザーの行動を分析し、改善点を見出しましょう。ページビュー数や滞在時間、離脱率、コンバージョン率などのデータをもとに、定期的にランディングページを更新し、成果の向上を目指します。
ランディングページ(LP)の構成・ワイヤーフレーム作成の流れ
の構成・ワイヤーフレーム作成の流れ-1024x538.jpg)
ランディングページの目的や種類により、構成や制作フローは異なります。以下は、その一例です。
- ターゲットの疑問点を洗い出す
- 訴求点をリストアップする
- 構成を組み立てる
- 伝えたい情報を効果的にレイアウトする
それぞれの流れでどういった作業を行うのか、詳しく見ていきましょう。
1.ターゲットの疑問点を洗い出す
ランディングページの構成を考える際の最初のステップは、ターゲットユーザーの疑問や悩みを洗い出すこと。ターゲットを具体的に想像し、そのユーザーが感じそうな疑問や不安を列挙します。
たとえば、初心者向けのプログラミング学習サービスのランディングページを作成する場合、リサーチや取材を通じて次のような疑問や不安を明確にすることが重要です。
- 「初心者でも理解できるのか?」
- 「どのくらいの期間で習得できるか?」
- 「プログラム終了後に実務でも通用するのか?」
- 「オンラインで本当に効果的に学習できるのか?」
- 「途中で挫折しないか?」
- 「費用対効果は十分か?」
このように疑問点や悩みを明らかにすることで、ランディングページで解決すべき課題が浮かび上がります。ターゲットのニーズにあわせた訴求ポイントや、適切な表現も掴みやすくなるでしょう。
2.訴求点をリストアップする
次に、明確になったターゲットの疑問や悩みに対応する訴求点をリストアップします。サービスや商品の特徴、メリット、他社との差別化ポイントなどを幅広く列挙していきましょう。たとえば、プログラミング学習サービスの例では、以下のような訴求点が考えられます。
- 「初心者でも安心して学べる、わかりやすいカリキュラムを提供」
- 「経験豊富な講師による充実したサポート体制」
また、プログラムを終えた受講生にインタビューを行い、実際に仕事で役立っているかなどをヒアリングするのも有効です。
こうして訴求点を整理することで、ランディングページで強調すべきメッセージが明確になり、ユーザーの疑問や不安を解消するコンテンツを効果的に作成できます。
3.構成を組み立てる
ユーザーの疑問や訴求点が明確になったら、それぞれの要素を効果的に配置するため、ランディングページの構成を組み立てます。ユーザーの心理状態や情報の重要度を考慮し、伝わりやすい順序で情報を配置することが重要です。
▼一般的なランディングページの構成例
- 主要な価値提案(キャッチコピー)
- 主要な特徴や利点の紹介
- 社会的証明(顧客の声、実績など)
- 補足説明(FAQなど)
- CTA(行動喚起)
情報を段階的に伝えることで、ユーザーがページを読み進める中で感じる疑問や不安を一つずつ解消できます。こうして関心が高まることで、最終的には申し込みや購入といった行動に結びつきやすくなるでしょう。
4.伝えたい情報を効果的にレイアウトする
最後に、決定した構成にもとづいて具体的なレイアウトを作成します。この段階では、以下のような要領でイラストやアイコンなどの視覚的な要素を効果的に配置し、ユーザーがページ内容を理解しやすく、アクションを起こしやすいデザインに仕上げます。
- 重要な情報は画面上部に配置する
- 視覚的階層を作り、情報の重要度をわかりやすく表現する
- 適切な余白を設け、読みやすさを確保する
- CTAボタンは目立つ位置に複数配置する
ここまで解説してきた流れでワイヤーフレームを作成することで、ユーザーにとって魅力的で説得力のあるランディングページを作成できるでしょう。
ランディングページ(LP)制作のポイント【要素別】
ランディングページは、以下3つのパートに分けて考えることができます。
- ファーストビュー
- ボディコピー
- クロージング
各パートの詳細と制作時のポイントについて見ていきましょう。
ファーストビュー

ファーストビューとは、ユーザーがページを開いた際に最初に目に入る部分のこと。この部分でユーザーの興味を引き、滞在を促すことが重要になります。ファーストビューは、主に以下の3つの要素で構成されています。
キャッチコピー

キャッチコピーは、ユーザーの関心を引きつける短いメッセージであり、商品やサービスの最大の魅力や特徴を、簡潔かつインパクトのある言葉で表現するものです。
たとえば、「1日30分でプログラミング習得!」や「たった3週間で理想の肌へ!」といったものが挙げられます。効果的なキャッチコピーは、ユーザーの課題解決や願望の実現をイメージさせ、より強く関心を引きつけます。
メインビジュアル画像

メインビジュアル画像は、製品やサービスのメリットを視覚的に伝える重要な要素です。ユーザーが商品を使用して満足している様子や、サービス利用後の理想的な状態を示す画像が効果的です。
たとえば、プログラミングスクールの紹介では、生徒が楽しそうにコーディングしている姿や、卒業生が企業でいきいきと働いている様子を表現するといいでしょう。ダイエット商品では、使用前後の比較写真を活用すると説得力が増します。
CTA
CTA(コール・トゥ・アクション)は、ユーザーに具体的な行動を促す要素で、ボタンやバナー、テキストリンク、フォームなどが該当します。
CTAには「無料カウンセリングを予約する」「今すぐ購入」など、行動を促すはっきりとした言葉を使うことで、ユーザーがアクションを起こしやすくなります。
また、CTAは色彩や大きさを工夫してページ内で目立つようにデザインし、「今なら30%オフ」といった特典情報を周囲に添えることも効果的。こうした工夫により、ユーザーの視線を引きつけ、行動を促しやすくなります。
ボディコピー
ボディコピーとは、ランディングページの本文部分のこと。製品やサービスの詳細情報を伝え、ユーザーの購買意欲を引き出す役割があります。
以下にボディコピーの主要な要素を紹介しますが、要素の順番や内容はランディングページごとに大きく異なることもあります。
問題提起
問題提起は、ユーザーが抱える課題や悩みを明確に示し、共感を得るためのセクションです。たとえば、「独学で挫折していませんか?」「肌荒れにお悩みではありませんか?」といったように、ターゲットユーザーの悩みに具体的に言及します。
こうした問いかけによって、ユーザーは自分の課題を再認識し、解決策への興味が高まります。問題提起の後にその解決策となる商品やサービスを紹介することで、ユーザーの関心を自然に製品へと導くことができるでしょう。
ベネフィット
ベネフィットでは、製品やサービスがもたらす具体的な利益を明確に伝えます。「就職支援サービス付きで、卒業後3ヶ月以内の就職率98%」「時短家電で毎日の家事時間を半減!」など、ユーザーにとって魅力的な内容を提示しましょう。数値やデータを用いることで、説得力をさらに高められます。
実績
実績では、過去の成果や成功事例を示すことで、商品やサービスの信頼性を高められます。「累計販売数10万個突破!」「利用者満足度98%」といった具体的な数字で実績を示すと効果的。また、著名な企業や団体との取引実績やメディア掲載歴なども、信頼性の向上に役立ちます。
専門性
専門性では、商品やサービスに関わる専門知識や技術を紹介し、その信頼性を裏付けます。たとえば、「〇〇大学との共同研究により開発」「特許取得済みの独自技術を採用」といった形で、科学的根拠や技術的優位性を示しましょう。また、開発者や監修者の経歴や資格を紹介することで、商品の専門性をさらに強調できます。
活用シーン
活用シーンでは、商品やサービスが実生活でどのように役立つかを具体的に描写します。たとえば、「平日夜間・土日開講で、仕事や学業と両立できる」「オンライン受講対応で、全国どこからでも参加可能」といったように、ユーザーの日常生活に即した使用例を提示しましょう。
お客様の声

お客様の声では、実際の利用者からの感想や評価を紹介します。たとえば、「未経験から3ヶ月でIT企業に内定しました(28歳男性)」「英語力が向上し、海外出張が楽しみになりました(40代男性)」といった具体的な体験談を掲載しましょう。可能であれば、写真や名前(イニシャルでも可)を添えることで信憑性が高まります。
また、さまざまな年齢層や背景を持つ顧客の声を紹介することで、幅広いユーザーに共感してもらいやすくなります。
専門家などの推薦
専門家などの推薦では、商品やサービスに対する第三者からの評価や推薦を紹介します。たとえば、「○○大学医学部教授も絶賛」「著名なスポーツトレーナーが推奨」といった形で、権威ある専門家の評価を示しましょう。これにより、商品の信頼性と専門性がさらに強化されます。
料金などの比較表
料金などの比較表では、自社製品と競合他社製品を比較し、自社の優位性を視覚的に示します。価格や機能、サポート内容など、ユーザーにとって重要な項目を設定し、一目で違いがわかるよう表にまとめましょう。また、自社の各プランの違いを説明するのも効果的です。
よくある質問
よくある質問(FAQ)では、購入前のユーザーが抱きやすい疑問や不安に答えます。「返品・返金は可能ですか?」「副作用はありますか?」「どんな支払い方法がありますか?」などの質問と、その回答を用意しましょう。
よくある質問は、ユーザーの潜在的な不安を解消し、行動への障壁を取り除くために重要な役割を果たします。
クロージング
クロージングはランディングページの最終セクションで、これまでのコンテンツで醸成した興味を具体的な行動へとつなげます。たとえば、「今すぐ申し込む」といったCTAボタンの周囲に「30日間全額返金保証付き」「初回購入者限定50%オフ」といった情報を配置し、ユーザーの決断を後押しします。
また、「在庫限り」や「期間限定」といった緊急性を感じさせる文言も効果的。クロージングでは、ユーザーの懸念を取り除き、スムーズに購入や申し込みへと導くことが重要です。
ランディングページ(LP)の制作方法・手段
ランディングページを制作する方法には、Web制作会社への依頼、自社での制作、フリーランスへの依頼の3つの選択肢があります。大まかな費用の目安は以下のとおりです。
| 制作方法 | 制作費用の目安 |
|---|---|
| Web制作会社への依頼 | 簡単なLP:10万円〜30万円 中規模なLP:30万円〜70万円 高機能なLP:70万円〜150万円以上 |
| 自社での制作 | LP作成ツール使用:無料〜月額10,000円程度 |
| フリーランスへの依頼 | 簡単なLP:5万円〜15万円 中規模なLP:15万円〜30万円 高機能なLP:30万円〜50万円以上 |
それぞれの方法のメリット・デメリットについて詳しく解説します。
Web制作会社への依頼
Web制作会社に依頼すると、ランディングページを高品質に仕上げてもらえるため、最も信頼性の高い選択肢といえます。専門的なスキルと経験を持つチームが制作を担当するため、デザイン、コーディング、SEO対策など、総合的に質の高いページが期待できます。
ただし、複数の担当者によるチェックが入るため、制作期間が長くなりやすい点がデメリットといえるでしょう。
自社での制作
自社での制作は、費用を大幅に抑えられることが最大のメリットです。自社の意図を直接反映できるため、迅速な修正や更新も可能になります。
ただし、自社に専門的なデザインやコーディングのスキルを持つ人材がいない場合、企業としてふさわしい品質のランディングページに仕上がらない可能性も。また、制作には社内リソースを割く必要があり、他の業務に支障が出る点にも注意が必要です。
フリーランスへの依頼
フリーランスへの依頼は、Web制作会への依頼と自社制作の間に位置する選択肢です。制作会社よりも安価で、専門的なスキルを活用できる点がメリットです。
ただし、個人への依頼であるため、相手の経験やスキルによっては、期待していた品質と大きく異なるリスクも。また、納期の遅延などのトラブルが発生しやすい点もデメリットといえるでしょう。
ランディングページ(LP)制作を成功させるための4つのコツ
ランディングページの制作を成功させるためには、以下の4つのコツを意識してみてください。
- ユーザーのニーズに寄り添う
- 制作後もPDCAを回し続ける
- レスポンシブデザインに対応する
- 誰でも理解できるわかりやすさを意識する
それぞれのコツについて詳しく見ていきましょう。
1.ユーザーのニーズに寄り添う
ユーザーのニーズを理解し、それに応える内容を提供することが、訴求力の高いランディングページを制作するコツになります。
たとえば、アンケートやユーザーインタビューを通じて、ターゲット層の課題や悩みを直接聞き取る方法がおすすめです。得られた情報をもとにペルソナを設定し、そのペルソナが求める情報や解決策をランディングページに記載することで、具体的で訴求力のある内容に仕上げられます。
2.制作後もPDCAを回し続ける

ランディングページは公開後も、継続的な改善が欠かせません。アクセス解析ツールを用いてユーザーの行動を分析し、問題点を特定しましょう。
たとえば、離脱率が高いセクションがあれば、そのコンテンツや設計を見直すと改善が期待できます。また、A/Bテストを実施して、異なるデザインや文言の効果を比較するのも有効です。定期的に解析と改善を重ね、コンバージョン率の向上を目指しましょう。
3.レスポンシブデザインに対応する
スマートフォンやタブレットなど、さまざまなデバイスからのアクセスに対応するために、レスポンシブデザインは欠かせません。画面サイズに応じ、自動で最適な表示に調整されるよう設計することで、どのデバイスからでも快適に閲覧できるようになります。
特に、近年はモバイル端末での閲覧が主流のため、スマートフォンでの表示を優先する「モバイルファースト」の設計思想が重要に。画像のサイズ調整やボタンの配置など、タッチ操作に適したデザインを心がけましょう。
4.誰でも理解できるわかりやすさを意識する
ユーザーが瞬時に理解できるよう、わかりやすさを心がけることが重要です。専門用語を使用する場合は、可能な限り定義や説明を加え、配慮した表現にしましょう。
また、グラフや図表、アイコン、動画などの視覚的な要素も活用し、スムーズに理解してもらえる工夫が求められます。
ランディングページ(LP)制作の制作事例
ランディングページ制作の参考として、弊社のLP制作事例を3つご紹介します。いずれもレスポンシブデザイン対応で、さまざまなデバイスから快適にご覧いただけるLPとなっています。
事例1.扇風機のランディングページ

扇風機のランディングページ制作では、メインビジュアルから細部に至るまで、自社スタジオで撮影した写真を使用しました。「あらゆるシーンに心地よい光と風を」というキャッチコピーを軸に、製品の使用感や快適さを多面的に表現しています。
製品の特徴は簡潔なアイコンで表し、独自技術の説明を加えて製品の強みを明確に伝えている点もポイントです。また、白を基調とした爽やかな配色により、製品のクリーンなイメージを強調しました。
これらの要素を取り入れることで、ターゲットユーザーの興味を引き、魅力的なランディングページに仕上がっています。
参考:【LP】家電・扇風機のランディングページ制作_ファイテン株式会社様|Web制作なら東京・京都のJPC
事例2.食品のランディングページ

引用:乾燥しがちな肌とひざ関節の違和感に | グルコサミン炭酸水 伊藤園
40代以上の女性をターゲットに、商品の世界観と健康価値を伝えるランディングページを制作しました。お客様からは「商品の魅力をイラストで表現し、健康価値をわかりやすく伝えたい」とのご要望をいただき、弊社でオリジナルイラストを作成。各セクションにイラストを活用することで、商品の特長を視覚的に伝えやすいデザインを構築しました。
さらに、パソコンやスマートフォンを含むさまざまなデバイスで快適に閲覧できるよう、レスポンシブデザインを採用。ランディングページ制作にとどまらず、バナーやポスター、POPなどの販促ツールも一括して制作し、プロモーション全体に統一感を持たせています。
参考:【LP】食品のランディングページ制作_株式会社伊藤園様|Web制作なら東京・京都のJPC
事例3.化粧品・コスメのランディングページ

引用:パートナーと共に美しく「シェアドコスメ」TOWAZトワズ
性別を問わず使用できるジェンダーレスコスメのランディングページを制作しました。商品のコンセプトに合わせ、性別を限定しないジェンダーレスなトンマナを意識しながら、商品パッケージの色味を活かしたデザインに仕上げています。
「絆が深まる」という商品の特長を視覚的に表現するため、優しいタッチで手と手が取り合うイラストを作成し、メインビジュアルに採用。視覚的な温かみと普遍性を演出しました。
また、レスポンシブデザインを採用し、パソコンやスマートフォンなど、さまざまなデバイスで快適に閲覧できるように設計しています。商品の撮影は弊社の自社スタジオにて行い、撮影から制作までワンストップで対応しました。
参考:【LP】新商品のブランドサイト制作(TOWAZ)_株式会社マックス様|Web制作なら東京・京都のJPC
ランディングページ(LP)制作でよくある質問
ランディングページの制作をWeb制作会社に依頼する際に寄せられる、よくある質問をご紹介します。
納品されるまでの期間は?
ランディングページの制作期間は、プロジェクトの規模や内容の複雑さによって異なりますが、一般的な目安としてシンプルな1ページのLPであれば、約1か月で仕上げることが可能です。ただし、ページ内容やデザインの複雑さ、撮影の有無などにより、この期間は前後することがあります。
段階的な公開に対応しているWeb制作会社もありますので、急ぎの案件はこうした対応が可能な会社に依頼するとよいでしょう。
納品方法・形式は?
一般的には、完成したデータをお渡しする方法と、直接サーバーにアップロードする方法があります。WordPressなどのCMSを使用する場合は、サーバーへの直接アップロードが基本となります。
まとめ
ランディングページ制作では、コピーライティングやデザイン、コーディングなど、多岐にわたる要素への配慮が必要に。自社内製やフリーランスへの依頼よりも、各分野のプロが揃うWeb制作会社に依頼することで、目的に沿った高品質なランディングページが実現しやすくなります。
株式会社ジェー・ピー・シーは豊富な実績を持ち、クライアントのニーズにあわせた効果的な構成とデザインを提供しています。
当社のサービスは、以下の特徴を備えており、ランディングページの成果向上をサポートします。
- 戦略的なキーワード設計によるSEO対策
- ユーザー行動を促すデザインと操作性
- 更新しやすいWordPress対応や高度なカスタムLP
- 公開後の分析と改善サポート
Webマーケティングの成功を支える高品質なサービスを提供しておりますので、ランディングページ制作をご検討の方は、ぜひ一度ご相談ください。

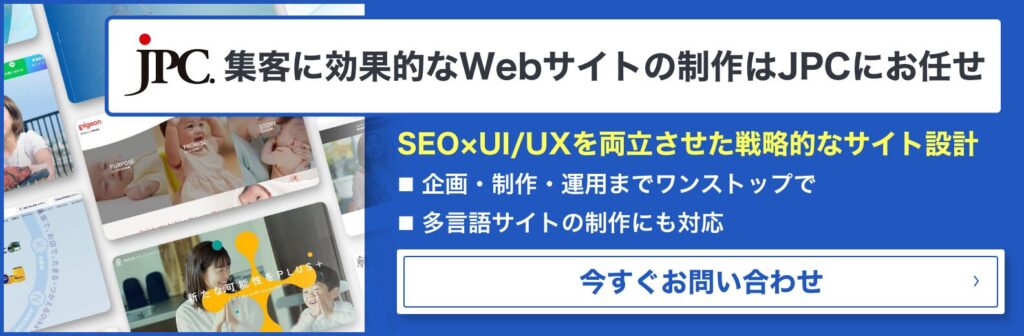
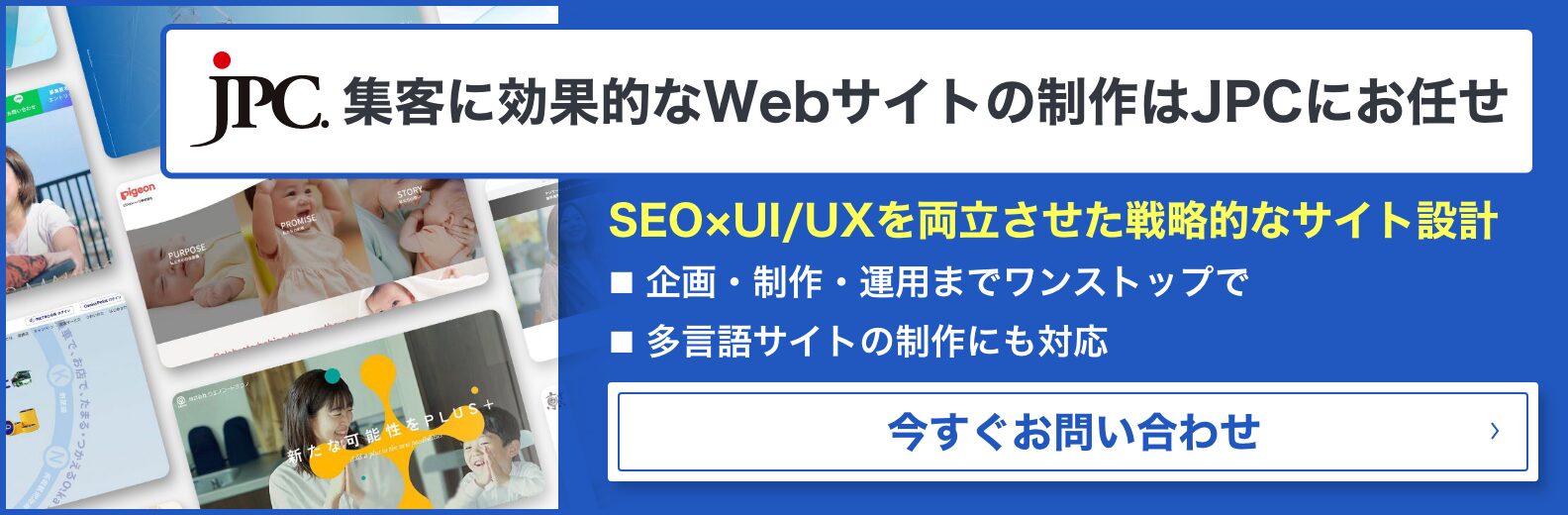


とは?目的やメリットを徹底解説-300x158.jpg)